急ブレーキかかった欧州「2035年EV化法案」。日系メーカーの「二正面戦術」は正しかった コメント「わりと皆最初から分かってた」「日本以上に中国が覇権を取る状況は欧米にとっては最悪」「世界中のEV車全部の電力、原発や火力発電所が大量に必要」

Photo by Cook aynne on Unsplash
急ブレーキかかった欧州「2035年EV化法案」。日系メーカーの「二正面戦術」は正しかった
3/9(木) 20:00配信 BUSINESS INSIDER Yahoo!ニュース
2021年7月14日、欧州連合(EU)の執行部局である欧州委員会は「気候変動対策に関する包括的な法案の政策文書(コミュニケーション)」を発表した。その中で、EUでは2035年以降の新車登録を、いわゆるゼロエミッション車(走行時に二酸化炭素などの温室効果ガスを排出しない車両)に限定する方針を示した。
ゼロエミッション車には電気自動車(EV)と燃料電池車(FCV)などが含まれるが、EUは実態としてEVを念頭に置いている。この欧州委員会の提案(以下、2035年EV化法案)は、2022年10月に欧州委員会、欧州議会、閣僚理事会の三者間で最終合意に達し、2023年2月14日に立法機関である欧州議会で採択された。
残るは3月7日に予定されていた閣僚理事会(EU各国の閣僚から構成される政策調整機関)での承認だけだったが、この会合が土壇場で延期される事態となった。ドイツのフォルカー・ウィッシング運輸・デジタル相が、ここへ来て“ゼロエミッション車にe-fuelのみで走行する内燃機関(ICE)車を含めない限り、法案を支持しない”と表明したためだ。
ドイツが「不支持」の背景…「e-fuel」がなぜキーなのか
e-fuelは再エネ由来の水素を用いた合成燃料のことだ。燃焼時には二酸化炭素(CO2)を排出するが、一方で生産の過程でCO2を利用するため、CO2の排出量と吸収量を差し引けば実質ゼロとなる。また既存のガソリン車やディーゼル車にも使えるという特徴がある。一方で、製造効率が悪いため、生産コストが高くつくという問題を抱えている。
このe-fuelの利用を推進しようとしているのが、実はポルシェに代表されるドイツの自動車メーカーだ。e-fuelであれば、既存のガソリン車やディーゼル車の生産ラインを維持できる。そのため、ショルツ連立政権に参加する自由民主党(FDP)は、親ビジネスの立場からe-fuelの利用を重視する。ウィッシング運輸相は、そのFDP出身だ。
欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長が説得にあたったが、ウィッシング運輸相やFDP党首のクリスティアン・リントナー財務相は首を縦に振らなかったようだ。引き続き、フォン・デア・ライエン委員長は説得を試みている。なぜならば、ドイツが賛成に回らない限り、閣僚理事会で2035年EV化法案が承認されないためだ。
イタリアやポーランドも法案に合意せず
閣僚理事会の採決は特定多数決によって実施される。つまり「EU27カ国のうち15カ国以上の同意が不可欠」であるとともに、その「15カ国でEUの人口の65%以上を占める」必要がある。ドイツだけの反対なら、2035年EV化法案は承認される運びだが、問題はドイツ以外にもこの法案に合意していない国があることだ。
まずイタリアが、この2035年EV化法案に反対している。イタリアのメローニ右派連立政権は、親ビジネスの立場に加えて、EVシフトが雇用に与える悪影響を重視している。従来のガソリン車やディーゼル車の生産ラインが不要となり、雇用が失われる恐れがあるため、EVシフトは慎重に行うべきだというのがメローニ政権の立場だ。
その他にも、中東欧の大国、ポーランドが反対の意見を表明、ブルガリアも棄権に回るようだ。ドイツとイタリア、ポーランドの人口を合わせると約1億8000万人、EU全体の人口がおおよそ4億5000万人であるから、4カ国の人口を合計すると35%を超えることになる。つまり、2035年EV化法案は閣僚理事会で否決となる。
全文は以下(BUSINESS INSIDER)
https://www.businessinsider.jp/post-266777
関連
上記のように、ドイツの「e-fuel」提案は「ガソリン車を販売禁止にするな!」と同じ。
— 井上雅夫(脱・脱炭素派) (@co2tw) March 8, 2023
脱炭素を主張するドイツは、これを正直に言うことができないので、「脱炭素燃料e-fuelを使えるようにしろ!」と主張。
ドイツの脱炭素は建前だけで、本音は脱・脱炭素。
ずるいドイツに騙されてはいけません!
【EU内でも異論】ドイツには、EUの2035年のガソリンとディーゼル車禁止令を乗り切るために、E-Fuel ICE車を希望する意見もある - TopGearJapan
https://topgear.tokyo/2023/03/57726
海峡の向こうで、ドラマチックな出来事が起きている。2035年から燃焼式エンジン車の販売を全面的に禁止することが承認された後、ドイツでは、合成燃料を使用する燃焼式自動車が禁止の対象から外れるのではないかという懸念の中、この法案を正式に採択するための最終投票を中断させた。
ドイツのフォルカー ヴィッシング運輸相は、ツイッターで次のように述べた。「内燃機関そのものが問題なのではなく、それを稼働させる化石燃料が問題なのです」
ドイツがヨーロッパ最大の自動車生産国であり、82万人の雇用を守り、合成燃料産業に多額の投資をしていることは、間違いなくプレッシャーにもなる。
Der Verbrennungsmotor an sich ist nicht das Problem, die fossilen Kraftstoffe, mit denen er betrieben wird, sind es. Klimaneutralität ist das Ziel und zugleich eine Chance für neue Technologien. Wir müssen dazu offen sein für verschiedene Lösungen.
— Volker Wissing (@Wissing) March 5, 2023
コメント
わりと皆さん最初から分かってましたよ。
今の欧州の状況じゃ時期尚早です。
ディーゼルエンジンを進めて イニシャチブを取れなくて EVへ振ったけど それも無理
日本車排除を狙ったけど EVなら今度は中国の進出が不安 まあ予想通りでした。
日本はEVも開発しながらハイブリッドやPHEVを進めて行けばいいと思いますね。
あと12年後に完全EV化は、雇用問題、関連部品メーカー問題、バッテリーなどの製造設備問題などなどとても現実的とは言えない。欧州委員会はIPCCや国連の思うままであるから経済問題や雇用問題などは目に入らないのだろう。急進派だったドイツもいつものように手のひらを返した。当然の成り行きだ。
日本はこれまでいかにも翻弄されてきた。ここらで目を覚ましてじっくりと考え直すべきだろう。完全EV化はあり得ないのだ。
環境重視派こそが私腹を肥やしたい金儲け重視派だろう。車だけ燃料を使わないで他はこれまで通り石油を使うなら詐欺に近い。そんなに石油を目の敵にするならEV生産に使う石油精製品は100%リサイクル原料か100%石油由来製品以外のものを使うべき。石油を精製すれば嫌でも燃料ができて使わないなら余るだけ。どうせ途上国などに売って結局は消費させるつもりだろう。EVで環境保護など余りにも遠回りの屁理屈政策すぎる。
自動車産業はどの国でも雇用の受け皿なので、ここが反対勢力になるだろう…ってのは予想通りでした。
メルセデスに加えてアウディ、ポルシェまでがe-fuel燃料を使う2026年F1に参入の意を示した事から、ドイツ勢がルール変更を思惑しているのも予想通りでした。(ポルシェのF1参戦は頓挫気味)
今後の展開は、EV推進が中国を肥やす政策なので、国防サイドからの強い抵抗が予想されます。
他には、現在でも高価で世界的に補助金頼りのEV拡販ですが…記事にも指摘されているように安いクルマを開発しないと末端までの普及は望めません。しかしここに大きな矛盾があります。限りあるレアメタルを大量に使用するEVは、普及するに連れて資源が枯渇する。価格は高騰して行く運命にあります…
あらゆる側面から、全ての自動車がEVに変わる未来は無いと思います。
元々、航空機や船舶はEV化が難しいでしょう。自動車だけがターゲットになったのに違和感を覚えていた。石油だって、何で出来ているかを考えたら、太古の昔のプランクトンが原料らしいが、プランクトンだって大気中や海中のCO2を取り込みながら活きていた生物だ。自然界のCO2を取り込んだものなら、e-fuelと同じく、ゼロエミッションじゃないですか。炭素は、単に自然界を循環しているだけなのに、悪者扱いされるのですね。
確かに、全てEV車化は時期尚早ではあるが、車からは排出物は無くなることは確かたが、充電する電気は発電所で作り、EV車が増えればその分発電量は増える。発電量が増えれば、火力発電所であれば二酸化炭素の量はかなり増える。原子力発電であれば二酸化炭素は増えないが、危険性は増えるかと。
それ以外の太陽光や風力等では発電量が少なく発電量にムラがある。
そこは考えているのだろうか?
欧米のEV推進の戦略は本質的な環境対策ではなく、自動車産業のイニシアティブを取っていくための手段でしかない。
現実的に考えれば環境保護に対する手段は地域ごとに異なるのは明らか。
環境対策に優れた手法が電気の地域もあれば、従来の原動機の地域もある。
グローバルで展開してるメーカーであればICEやHV、FCVやEVなど多方面で投資を続けるのが正解だろう。
BEVでは物量に優る中国にシエアを奪われるかもしれないが、ICEなら中国は全く歯が立たない。e-fuelを選択肢に入れることは、少なくともドイツやイタリアにとっては最良の選択だ。モータースポーツはe-fuelで継続の方向だし、高い技術を保有する欧州が早々にエンジンに見切りをつけることはないと思う。
性急なEV化はやはり無理がある。まだ技術開発が追いついていない。EVを製造する為に多くのCO2を排出してCO2削減効果がほとんどない。バッテリーに多くの希少金属を使い、希少金属採掘により環境破壊が発生する。10年くらいで大量のバッテリーの廃棄物が出るがリサイクル技術が十分確立されていないので埋め立てによる土壌汚染が広がる可能性がある。モーターを作るために大量の銅が必要であり銅資源が足りない。電気の供給は火力発電ではCO2が減らないので、火力発電を減らせば原子力発電所の増設が必要になる。バイオ燃料が、カーボンニュートラルと認められているので、e-fuelは現実的な選択肢だと思います。
BEV至上主義者の多くは何らかの利害関係でポジショントークしているように思えてならない。BEVの普及って結局電池の覇権を握っている中国を利するだけ。
一般消費者で高額かつ充電器の取り合いになるBEVを買いたいと思う人って何パーセントいるんだろう?
かと言ってe-fuelや水素を含む合成燃料も製造の非効率性から大量生産技術が確立できないと普及へのハードルはなかなか高い。
電力会社やゼネコンが研究している走行中のワイヤレス給電技術とかどうなのかな。充電器の取り合いになる心配もないし、直接電気を使うから効率性も高いはず。
最低限のバッテリを積んでいれば主要道路におけるインフラ整備だけでいけそうだし、公共事業として経済対策にもなり充電器をバラバラで整備して保守するよりも効率的なはず。
まあどんな方式であれ否定するのは簡単だけど技術的ブレイクスルーはあり得るので日本企業の底力見せて欲しいな。
すべてEVにしようにもリチウムの供給が追いつかなくなる。CO2にしても100台の内燃機関車のうち1台をEVにするより同容量のバッテリーでハイブリッド車を90台作るほうがCO2を30倍削減出来るというデータをトヨタのCSOが発表している。様々な方法で削減していくべきでEV一択と言うのはやはり無理がありすぎる。
こうなる事は明白だった。EUの一人相撲に迎合しているメーカーはハシゴを外されてしまう。クルマのBEV化は必須だと言う人もいるが、地球上で見たらそれが可能なのはEUの極一部の国だけ。未だに生活に必要な基本的なインフラも整っていない国も沢山ある。それでもそれらの国でもクルマは走っている。結局EUはEUのことだけしか見ていない訳で、その為にクルマメーカーが全部BEVに転換なんて所詮無理な話で、それぞれの地域に適合したクルマを提供していく必要があるし、またそれがメーカーの責務でもある。
一部の先進諸国の先走りで物事は決められる物では無い。
目論見が外れたからですね。
エンジン開発で高い技術力がある日本には勝てないと思い、まだ日本が弱かったEV技術で覇権を取り返そうとした。
ところが中国がEVでかなり力を持ってきて、韓国もバッテリー関連で影響力がある。日本以上に中国が覇権を取る状況は欧米にとっては最悪の状況。ならまだエンジン車を活用したほうが良いと方向転換するのは無理もない。
欧州人はいつも自動車関係の規則を自分達の都合の良いように一方的に変更するから卑怯です。
①クリーンディーゼル⇒VWとベンツが排ガス不正で墓穴を掘るとやっぱり環境に悪いと方向転換。
②ハイブリッド⇒技術的に太刀打ち出来ないからと低公害車指定から締め出し。
で、今度はEVも自分達の都合の良いようにねじ曲げて行くのが目に見えている。
EVは街中の環境は確かに良くなるでしょうが、世界中のEV自動車全部の電力を賄おうとすれば、原発や火力発電所を大量に作らなければ足りなくなると誰も分からないのでしょうか?地球環境改善には全く寄与しませんよ。
https://news.yahoo.co.jp/articles/417cfc3c8c5008c757f7608384f59a68091354fd/comment


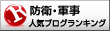
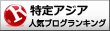



コメント
コメントを投稿